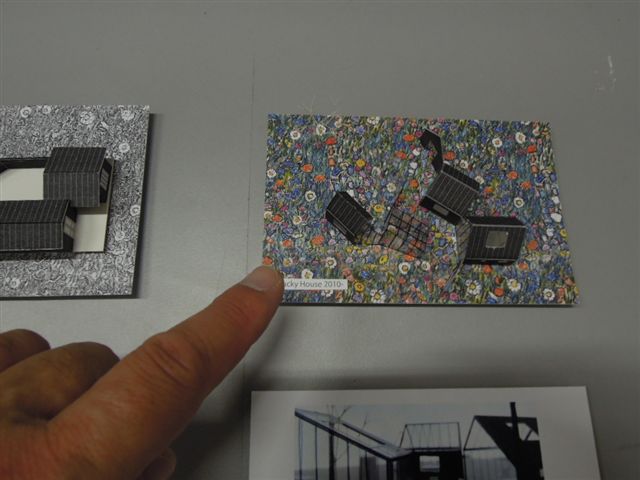過日、隣県の福井市へ出かけ、小、中学校を各一校づつ見学させていただきました。
これから始まる小学校現場担当の建設工事会社、我々設計監理者、総勢10人が午前中に小学校、午後から中学校を見て廻りました。事前にお願いしてあった事もあって、暖かい応対でありました。
どちらもプロポーザルで設計者が選定されたコンクリート打ち放しのモダンな学校です。
最初の小学校は教頭先生が案内して下さいました。
はじめは通り一遍のお話でしたが、そのうち「ひとりごとだと受け流してください。」と言いながら、あちこちの不具合についてお話されるようになりました。
「ガラス張りの吹き抜け空間は開放感があっていいんだけど、夏は暑い、冬は寒いんです。」
ごもっとも、さらに「この大きな布はなんだと思いますか?」・・・・・・・・・??
「ここに太陽の光が反射して眩しいんですよ」とのことで日除けとして布が広げてあるとか。
さらに風が通らないカーテンウォールと窓の開かない教室、などなど話は尽きない。
トイレに至ってはタイル張りはいいのだけど排水口がない、つまりドライ工法だ。ドライにしては仕上げの選択がいまいち、雑巾やモップが使いづらいとのこと、ごもっとも。
午後は越前そばをいただき、いざ中学へ。
ここも見学が多いようで当日も年配の方が5人ほど後ろに並んでいらっしゃいました。
実はそうではなく、地域ボランティアの方だったんです。
皆さん、ニコニコしながら校長先生の説明を一緒に聞き、その後案内をしてくださいました。
自分の孫が通っている方もいました。

この中学校の特徴は「教科センター方式」と言って教科のオープンスペースを中心にした異学年がグループ構成している特殊な方式でした。と言ってもなかなかわかりにくいと思います。
要は、今までの様なクラスルームが各学年ごとに並んんでいるのではなく、理科、数学、英語等の教科が主体となる構成で、そこに各学年から1クラスづつ、3学年がくっついている。という構成です。校内には廊下らしきものがなく、オープンスペースどうしが寄り添うように構成され自由な空間となっていました。
どちらの学校もプロポーザルで設計者選定がなされています。しかしながら出来上がった建物には随分と差があることが解りました。それは地域の方が一番感じているのではないかと思いました。大きくは後者はワークショップで学校や地域の意見を拾い上げていること。前者は設計者が偉大で要望を聞いてくれなかったようです。引き継いだ教頭先生が語ってくれました。悪いことは語り継がれるものなんだ・・・。
我々も真摯に耳をそばだてなければならないと感じ、こうあらなければならないと感じた見学会でした。 (T.T)